
【魔改造の夜】「ビニール傘滞空 マッチ」が 引き出した、東レの エンジニアリング精神
「子どものおもちゃ」や「日常使用の家電」がエンジニアたちの手によりモンスターへと改造される技術開発エンタメ番組「魔改造の夜」。生贄である「ビニール傘」に挑んだ東レのエンジニア18人。その中心に立ち、チームをとりまとめたリーダーの坂下、サブリーダーの中島と井上、そして、彼らをメンターとしてサポートした藤内に話を聞いた。2つの魔改造に向き合った18人のエンジニアが経験した挑戦の日々とは––。
※本記事は、特設サイトからの転載記事です。
「魔改造の夜」挑戦を決めた理由
―それぞれの担当業務と、今回の挑戦を決めた理由を教えてください。

坂下:私はコーティングを主とした流体プロセス開発を専門としています。普段は東レ内の生産装置で使う口金やスプレーノズルといった流体を扱う機器に携わることが多いです。大学時代から専攻していた流体力学や流体解析の知識を活かしています。
「魔改造の夜」では、今後、後輩も率いていく技術者としてより成長したいと考えリーダーに立候補しました。「ビニール傘滞空マッチ」チームのリーダーとして、みんなが気持ちよく開発できるように務め、一人のエンジニアとしては自由落下方式の「開く君へ」というモンスターの設計も担当しました。
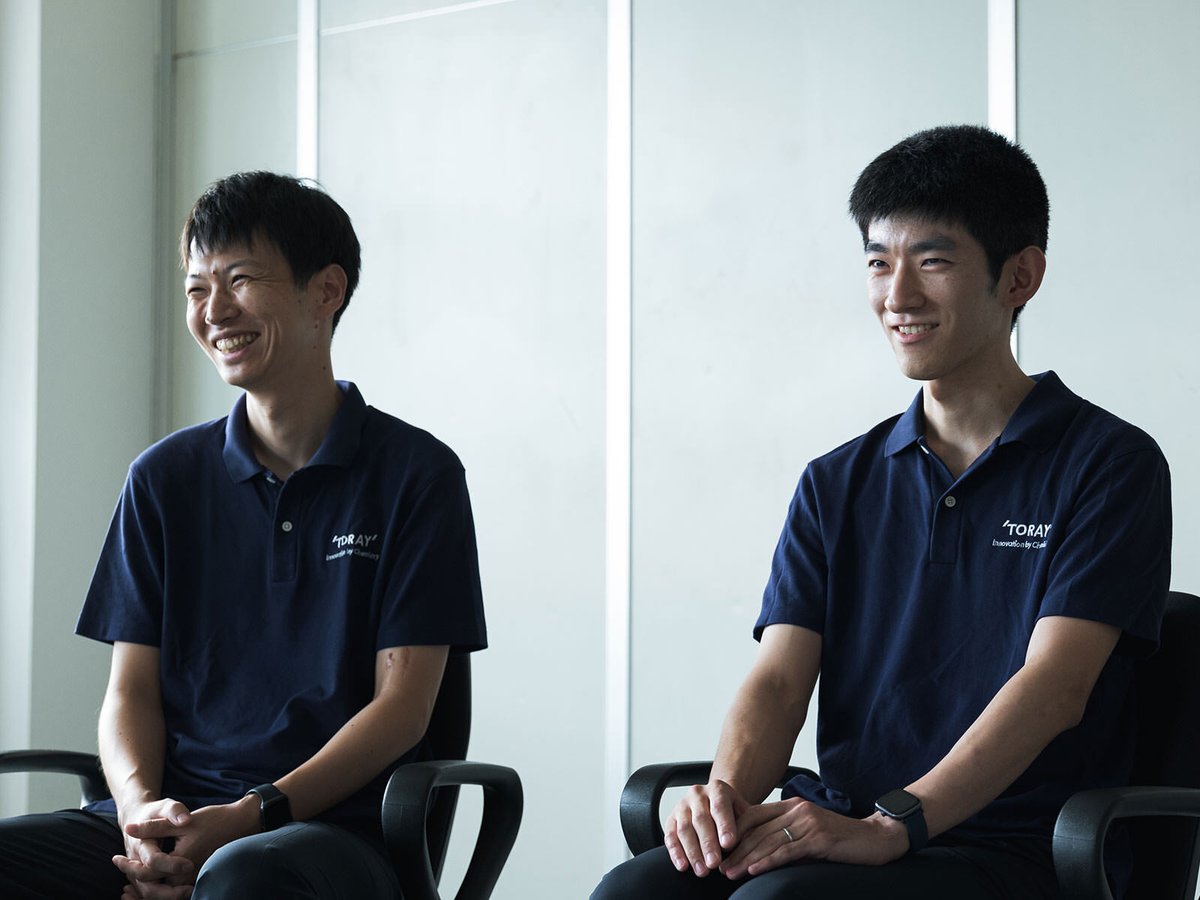
中島:私は水処理やガス分離に使われる分離膜モジュールの製品開発や生産装置開発を行っています。今回は「開く君へ」の統括として設計や加工に携わりました。
東レという素材メーカーで働いていると、素材は目立たないけれど社会生活では重要な「脇役的な良さ」があると思っています。一方で「魔改造の夜」は、他にはない自己主張ができ、「主役になれる」という点でも正反対の存在で魅力的に映りました。
井上:私は中島さんの下で海水の淡水化に使われる逆浸透膜などの水処理関連の製品開発、生産プロセス開発を担当しています。今回は羽ばたき方式の「うきうきアンブレラ」というモンスターの統括を務めました。
参加を決めたのは、学生時代に学生ロボコンサークルに入っていた経験を活かせるのではないか、と考えたのが理由の一つです。ロボコンをやっていたころのものづくりに対するわくわく感をもう一度味わえたらいいなと。

藤内:私は坂下君の上司でもありますが、東レのエンジニアリング開発センターにおいて「新事業グループ」のリーダーを務めています。研究で生み出された素材を工業化するためのプロセスや装置の開発が主な業務になります。
「魔改造の夜」では傘チームのメンターを担当しました。全体を見る坂下リーダーが頑張ってくれていたので、一歩下がったところから支援するように努めました。1ヶ月半、みんなと一緒に走り抜けて、リーダーが困っていることがあれば相談に乗ったり、チームメンバーをサポートしたりと、裏方的な立場での参加になりました。参加した動機は、普段の業務ではなかなか得られない「同じレギュレーションで他社エンジニアと競い合う」という経験をしたかったからですね。

―改造対象の「生贄」が発表されたときの率直な感想は?
坂下:事前に過去のお題で練習をしたり、チームで勉強会を開いたりして、生贄の予想はしていたのです。今までの番組の流れからすれば、家電で「アイロンあたりでは?」と踏んでいたのが、全く違う「傘」が来て。「えっ、何だこれ?」と正直思いましたね(笑)。
ただ、お題が「浮く」ということで言うと、私は流体力学だけでなく航空力学も大学で学んでいたので、「自分の土俵で戦える」と感じて受け入れるのは早かったかもしれません。
中島:私も大学時代、航空力学を専攻していて、業務でも流体力学を扱っているので、傘というお題は個人的にはフィットしました。ただ、「魔改造の夜」に参加するならもっとメカっぽいものに触れて、普段と違う領域を勉強したいなという気持ちも少しありました。傘となれば素材や軽さが鍵になるはずなので、東レの得意領域からすると負けられないお題だな、と気が引き締まりました。

井上:テーマ設定自体の面白さを感じました。滞空するとなると、空中で浮遊するのは非常に難しいだろうなと。番組側はどんなものが出てくることを想定してお題を設定したのか、今後の1ヶ月半で何をやればいいのか、まずはそこから考えましたね。バッテリーや圧縮空気を積んで自らの力で浮くのを想定しているのか、それとも動力源は一切ないものを想定しているのか……。
2つの魔改造で挑む決断の背景

―魔改造の方法はどのようにして探っていったのでしょうか?
坂下:本来なら、いろいろな可能性を試すために最初は複数の方向性で考え、最終的には本命のアイデアに絞って収束していくのが正しい進み方かとは思うのですが、内実を話すと、今回は収束できなかったんですよね。それで、自由落下方式の「開く君へ」と羽ばたき方式の「うきうきアンブレラ」の2案で製作を進めることになりました。というのも、やはり今回のお題は、とても目標設定が難しかったです。
「恐竜ちゃん缶蹴り」だったら30m飛ばすという明確な目標設定ができますが、傘の目標タイムは10秒なのか、1分なのか、3分なのか…実現性や勝ち目がどこにあるのか全く分かりませんでした。目標タイムをどこに置くかによって動力源を付けて重力に抗うか否か、開発の方向性が大きく変わってしまうので、非常に悩ましかったですね。そのため、動力の有無で2案にまで候補を絞ることはできましたが、それ以降は2チームに分かれたまま最後まで突っ走ることにしました。

井上:羽ばたき方式のチームでは「動力があってこその魔改造の夜だ!」という考えのメンバーもかなり多かった。その意見も理解できたので、2案で突き詰めたことは、結果的には良かったのかもしれませんね。
坂下:個人的には「1ヶ月半という短い開発期間で羽ばたきをものにするのは難しく自由落下方式が現実的な勝ち筋である」と考えていました。ただ、原理的には、羽ばたきのような動力を持っていないとタイムに限界がある。他社が動力をものにしていたら絶対に勝てない。そういう意見も多かったので、両方の案を残すことになりました。

藤内:確かに「羽ばたいてなんぼ、動かしてなんぼ」というアイデアを突き詰めたい熱意も伝わりましたし、とはいえ勝利の可能性が高いであろう自由落下方式も捨てきれない。「もう止められなかった」というのも正直なところです(笑)。2チームが1ヶ月半、こだわり抜いて突き詰めていって、最後はその努力の結晶が完成したという達成感がありました。
作って、投げて、検証する開発の日々

―2つのチームで、開発プロセスの連携などはありましたか?
坂下:共通化した部分もありますね。例えば、傘の持ち手は両方式とも共通の部品ですが、内部をくり抜いて徹底的に軽量化しています。また骨の部材には市販のカーボンパイプを用い、強度と軽さのバランスを見ながら適用する場所に応じて太さなどを調整しました。お互いに「とにかく軽量化したい」という点は一致していました。
「開く君へ」は、ろくろやダボと呼ばれる関節パーツも可能な限りカーボン樹脂部品を3Dプリントして作り直しています。結果的に「開く君へ」は114.5gまで軽量化できた。生贄傘の約0.36倍です。重さが10g変わるだけで滞空時間が1秒は変っていたので、かなり大きな成果でした。

中島:傘の布地にあたるフィルムの材質についても、かなり検討しました。フィルム材料に詳しいメンバーに、それぞれの素材の特性や撥水性などを調べてもらったりもしました。実験室には材質や厚み違いのフィルムサンプルがすでにあったので、実際に感触を確かめながら選ぶこともできました。そこは素材メーカーである東レの強みを活かせたかな、と思います。
藤内:進め方としては、朝にアイデアを出して、昼間に作ってみて、夜には1回飛ばしてみる。そして問題点を抽出して対策を考え、次の日にまた作るという繰り返しでした。本当は流体解析なども活用してみたかったところですが、実際に作って、投げて、挙動を見るという方が開発のスピードが早かったですね。
坂下:そうそう、3Dプリンターを夜中に走らせて、朝にパーツを回収して傘に組み込んで、飛ばしてみるということもやりましたね。これを毎日繰り返してとことん軽量化にこだわりました。

井上:各部材については、社内で特注品を作ることも検討しましたが、特に追い込みの段階には時間的な制約がありました。朝に「これが欲しい」と注文して翌日に届いても、その頃には検討が進んでしまって使わなかったこともありました(笑)。「開く君へ」は、隣で見ていたのですが、毎日のように自作パーツが増えていって、最終的にはもとの傘のパーツはほぼ残っていませんでしたね。持ち手と小さな関節部品くらいでした。
2つのマシンで本番へ
―本番でも良い成績を出すことができましたが、どんな感想を持ちましたか。
坂下:まずは勝つことができて嬉しかったのですが、それにも増して、「自分の考えがあながち間違っていなかった」という安心感が大きかったですね。ずっと自由落下方式が現実的な勝ち筋だと自分は考えていましたから。第一試技は絶対に「開く君へ」で行くと決めていました。開発の結果、滞空時間が「うきうきアンブレラ」よりも長かったからです。第二試技は他社が「開く君へ」では絶対に出せないタイムを出した場合、原理的に勝てる可能性がある「うきうきアンブレラ」で対抗する計画でした。ただ、実際は別の理由で「うきうきアンブレラ」を出すことになりましたが。

中島:競技相手のチームが羽ばたき方式で挑んでくる中で、現場では「東レは重力に抗わない選択をした」といった見方をされるシーンがあって。いやいや、ずっと開発は続けてきた、という自信もありましたし、私は自由落下方式の担当でしたが、第二試技では羽ばたき方式の「うきうきアンブレラ」を出すべきだ、と坂下リーダーに進言しました。いずれの方式においても技術的に勝てることを示したかった。
藤内:確かに、本番で競技相手のチームの「モンスター」を見て、本体の重さや推力などのスペックから、ある程度は滞空時間の予測もつきました。これは我々が自由落下方式、羽ばたき方式の両方を検討してきたからだと思います。
本番でも自由落下方式で記録8秒を出した後のメンバーの反応と、羽ばたき方式で記録4秒を出した後では喜びようが全然違いましたよね(笑)。
中島:そうそう、自由落下方式の記録8秒は、実は本番より長い時間を出せた成果もあったので、むしろみんなは「残念」という感じで。だから、羽ばたき方式でも記録4秒を出して競技相手のチームを上回れた時はすごく盛り上がりましたよね。開発中は、我々の二つの方式間でお互いをどこかライバル視するような局面もありましたけれど、本番で「羽ばたき方式も出そう!」という議論になれたのは印象的なシーンだったと思います。

坂下:二つのアプローチを最後まで突き詰めたことが結果的に良かったようです。目標タイムを決めてから手段を絞り込むようなことはせず、最後まで二つのアプローチで進めることで、柔軟にさまざまな可能性を検討できました。また、東レの「極限追求」という技術開発の理念を守り、それを「軽量化」という課題に対して突き詰めたことも、どちらの方式でも良い成績を残せた要因だったと思います。
藤内:結果として、毎日のブラッシュアップを重ねることで、自然と「極限追求」の姿勢が体現できていたのでしょうね。振り返ってみると、普段の東レらしい仕事のやり方が活きていたなと思います。
魔改造の経験を今後に活かす

―このプロジェクトを振り返って、どのような学びがありましたか?
坂下:リーダーとしては、自分の考えを押し通すだけでなく、メンバーの考えや気持ちをしっかり聞いてバランスを取ることの大切さを学びました。「魔改造の夜」の期間中は、それが十分にできていたとは言えないところもあります。お互いが気持ちよく仕事できるようにすることが重要なのだという気づきを、今後の仕事で活かしていきたいですね。
中島:私は「魔改造の夜」で、毎日のようにみんなでさまざまなアイデアを試したことを通じて、失敗を恐れずにそれを繰り返すことが、やはり大切なのだと思いました。試して、ダメで、試して、ダメで…を繰り返しても、素早くリカバリーしていけば短期間でもすごいものを創り上げられる。この経験を活かして、普段の業務でも、より自由にアイデアを出し、もっと積極的に試行錯誤していきたいと思います。また、そういう前向きな姿勢でまわりのみんなにも良い影響を与えていきたいです。
井上:普段はあまり関わりのない人たちとも一緒に開発できたのは良い経験でした。ものづくりに対する熱意や、それぞれのこだわりなど、みんなの意外な一面や能力を発見できたのも大きな収穫でしたね。
また、もともと「うきうきアンブレラ」は飛べることを最優先に開発を進めていましたが、終盤にチーム内で「これは傘と言えるのか?」という議論が起こりました。たしかに番組のルールをクリアすることばかりを意識しており、我々にとっての”傘の魔改造”とは何かというところを突き詰めて考えられていませんでした。このような考えは通常の業務でも同じで、単に決められた仕様を満たすだけでなく、開発・設計段階からあるべき姿を深く考え、追及し続けることで、結果としてお客様が満足し、世の中に受け入れられる製品を提供できるということを再認識させられました。この議論を経て、大幅な設計変更を行い、結果的に滞空時間は短くなってしまいましたが「傘」であることは担保されるものになったと思います。
藤内:メンターとして一歩引いた立場で参加しましたが、1ヶ月半の間でメンバーがどんどん積極的になり、自分の役割を見つけて関わっていく姿を見て、非常に頼もしく感じました。ベテランも若手も関係なく、みんなが積極的にアイデアを出し合う姿勢は素晴らしかった。今後もこのように、活力のある職場を作っていきたいと思います。

文:長谷川賢人
写真:上野裕二
編集:花沢亜衣

